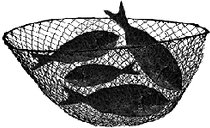Fushigina kaiko
不思議なかいこ
Ⅰ 作られていなかった予算
数年前まで、Kuroganeの町の大学には、予算という考え方がなかった。必要なものは、「原議書」という書類に記載をし、理事長あるいは学長の許可を得れば、購入できる。一人ひとりが必要なものは個人で申請する。小さな組織であれば、そういうシステムもありうるだろう。ただ、決裁者の覚えが良い人は、より決済を得やすいという弊害も生じやすい。
数個の学部で大学が構成される規模になると、組織全体で、どの程度の予算を使うかを決め、教育事業を実施し、将来の施設整備のために計画的に進めることが必要となる。Kuroganeの町の大学に、新しい学部を創設する際、予算システムがないなかで、せめて学部として計画的に教育事業を展開し、予算執行を行うことにした。どのくらいの予算規模を考えるべきなのか、法人からの指示はない。
そこで、学生の人数から収入を計算し、わかる範囲の支出項目を叩きだした。支出項目には、大学全体で行っている事業の学部負担分などもあるが、それは正確にはわからない。わかる範囲で、とにかくこの段階で「赤字」にしないことを基本に、学部予算案を作成(2008-2012年度)。完成年度までは、教育のための予算を優先し、研究のための高額な実験設備などへの投資を抑え、将来のスポーツ施設建設を法人が検討をするための基礎になるようにと説明資料を作成していた。
それが、2012年度になって、それらは「虚偽」の資料、教員にそんな資料を作る権限も能力もないと言い放たれてしまったら、何とかやりくりをしてきた数年は、いったい何だったのか。
Kuroganeの町の大学では、もちろん文科省に毎年報告をし、補助金を経るための学部ごとの収支決算報告も行っていたはずだが、2012年度までその情報の開示はなかった。教員の懲戒処分や解雇をめぐる法人側とのやり取りのなかで、
① 大学単体での決算は行っていない。
② 大学、学部の教育研究費は、2012年6月に新理事長就任後に新たに計算をし直した。
③ 理事長決済をうけていた学部の予算案は、理事会には出されていない。
などのことが責任者から明言された。
今になって、学園の責任者が、これら学部でなんとかやりくりするために作成してきた資料を「デタラメ」、虚偽として、作成者たちを名指しで叱責するのは、本当に不可思議だ。
Ⅱ ゆがむ組織、「規程は規程、実際は実際」
Kuroganeの町の大学には、昔カリスマ的な理事長兼学長がいたので、下から議論してボトムアップで何か決めていくよりは、「どこか」で決まった事項が学長列席の教授会で説明され、教員はそれをただ聞くだけというシステムだった。大学全体の学生部、学務部等の組織と、学部教授会、各種委員会などの
位置づけ、権限なども不明確。
カリスマ学長が逝去されて、新しい意思決定システムが必要となったとき、
組織は必要に応じて増加し、減少し、規定はあとから修正される。法の専門
家がトップになると、さすがに規定改正はきっちりと進められるようになった。
しかし、その規定改正の内容が、おかしい・不十分と疑義を呈しても、すでに
大学運営会議・評議会を通ってしまったものは、何を言っても始まらない。一部大学院の
授業料が下げられても、食堂の時間が変更になっても、どこでどう決めたのかさえよくわからない。
Kurogoneの町の大学には、もともと民主的な選挙による学長、学部長の選出という規定があった。ただ、カリスマのトップのもとで、それは暫定的に「指名」という形をとっていた時代がある。第三者評価でも、かなり前に指摘をうけ、改善するとの回答をしていたが、2011年、それは別の方向へ動き出す。学部創設時(2008年)に作成した学部教授会規則などの関連規程は、長い間「規程集」には掲載されず、大学事務局の机の引き出しにしまわれていた。
2011年夏、民主的な選挙とは反対に、学長、学部長の理事長による指名、学長による学科長指名へと大きく制度が変更。数か月にもわたる教授会での激しい議論の末、重要な規程は大学運営会議で承認されていればよいと幕引きされた。
Ⅲ 届かない保護者の悲鳴
学部の開設当時から、校舎やスポーツ施設の問題等を含め、多くの保護者の方々から要望が寄せられていた。学部の教育内容、まずは校舎の建設、キャリア教育など、学部への信頼を寄せていただくための説明会も、大学全体のものだけではなく、学部保護者会という形で開催していた。そのたびに、保護者は施設の将来計画は示されないのか、奨学金や教職希望者へのサポート体制はどうなっているのか、大学事務の対応のレベルアップ、大学の経営状態は大丈夫なのか、等々、実状をふまえてできるところの説明を学部運営担当者が行った。保護者は、育友父母会という形での活動も行い、大学の学生課や学生会役員会とも連携をとっていたが、大学および法人からの回答には大いに不満を抱えていた。
予算や、経営状況について、「学部については心配ない」「大学全体については、わかりません」などの理事らの大雑把な回答に不信感をもち、また入学時に大学が授業料と一緒に代理徴収を行っている「同窓会」の活動実態が見えないなど、多領域にわたる課題のなかには、数年にわたり幾度も提起した質問事項もある。保護者たちは、とりあえず学部運営メンバーの回答を求め、懇談をしながら、できるだけの意思疎通を図ってきていた。
2012年6月、大学父母会でも、経営状態や施設の建設計画など、質問が提起されたが、誠意ある回答がなされいないと保護者の一部は考えた。学部の運営担当者さえ、もはや法人と同じ姿勢を見せ始め、「一緒に力を合わせて」と呼びかける保護者に、「保護者は保護者で」と突き放してしまう。
10月20日の学部保護者会は、一部の保護者にとっては、意見表明ができる最後のチャンス。どのようにしたら、保護者の意見が大学側、法人側に届くのか。有志の教員も、保護者もそれぞれが知恵を持ちよって、誠意ある回答を引き出るにはどうするかと思案することになる。こうして、2012年10月6日の非公式な懇談会は、開催された。
Ⅳ 突然の叱責、キャリアセンター課長の左遷
2012年1月当時、キャリアセンター課長だった職員Aは、ある会議でいきなり学長補佐から非常に強い口調で叱責を浴び、連携する業者の選定、パンフの文言、業者側への疑惑などを列挙して攻め立てられた。その元課長は、大学局長の指示のもと、それまでKuroganeの町の大学では手薄だったキャリア教育と就職支援にテコ入れし、新学部の第一期卒業生の就職率も70%以上(卒業生に対する内定者の割合)をたたき出すという成果を上げていた。
職員Aは、業者の選定について、突き返されてくる原議書を何回も書き直し、コメントにすべて回答をし、支払いを業者に待ってもらいながら数か月のプログラムを走らせていた。その職員は、それだけの実績を上げながらも4月に突然異動となり、大学から外され、しかも降格人事だった。この降格での人事異動をめぐって、現在横浜地裁での訴訟が続いている。
その職員を叱責した学長補佐は、業者に不透明な部分があり調査中だと言い、2013年度になって行われた3社の業者によるプレゼンの前日、その業者は理由も告げられずに外された。いまだもって、不透明な資金の流れがあったのか、プレゼンから外す理由が何であったのかは、説明がない。
先に「理由がある、調査中」として、実際には事実を明確にもせずに人をたたき出しておいて、その後は何も説明もないというやり方は、無責任。Kuroganeの町の学園のなかの常識なのか、2名の教授解雇と通じる対応だ。
Ⅴ 度重なる問題提起と学部運営
2013年4月、新体制のもとでKuroganeの町の学部はスタートした。新しい体制のもとで、新たに示される運営方針や予算の件など、懸案は山積みだった。事務レベルでの体制がしっかりとしているところでは、多くの課題や作業の継続性が担保され、それらを土台にしつつ新しい施策づくりへと進んでいくことができる。しかし、Kuroganeの町の大学には、そうした組織体制はできていなかった。多くのことが、「〇〇先生に聞いてください」で済まされてしまっていたからだ。
学部の初めて体制移行は、運営責任者の方々の非常なる努力に支えられつつも、教授会では一つの案を練るために議論が数時間にも及ぶこともあり、同じ事項が何度もの教授会で議論が続けられることになる。でも、それは、教授会でいろいろ議論し、決めていくプロセスとしては、必要なこともあり、仕方のない部分もある。
しかし、予算については、法人との詰めが終わらないまま、どう執行できるのか不明確なまま、前期を終了せざるを得なかった。それは、学部の教育の展開に、どう責任をもっていくのかという問題と直結する。そのために、多くの問題提起をし、質問事項を提示し、意見の表明を行っていたのだが、後になってこれらはすべて「学部の運営の妨害」行為にあたると「認定」されることになる。
10月20日の保護者会で学生が文書を保護者に配付し、その学生が取り調べまがいの事情聴取をうけたことに異議を申立てた5名の教員が「譴責処分」という懲戒処分とされた。そこから、処分を受ける側は何も知らされないまま、何も聞かれないままに、どこからか一方的な報告書が法人トップに上がっていった。
Ⅵ そして、突然の解雇
Kuroganeの町の法人や大学にとっては、学生に「自分で判断し、問題と思ったことは提起し、社会を変えていく主体となれ、黙っていることで加担者となるな」と教育すると、学生を扇動したことにとなる。誰かが文科省に相談に行くと、リーダーの指示によって行っているに違いないとされる。保護者らからの質問状10通程度が出ると、それへの対応に「勤務時間内で到底収まりきらない仕事量となり」「迷惑」、業務妨害となる。もちろん、教授会での発言も、リーダーの指示に基づいた学部運営の妨害となる。
そして、2名の教授が、「グループのリーダー格」として、突然解雇された。
2013年
2月18日 2名の教授に対し、解雇の審議をする旨の説明書
3月11日 解雇処分に関わる陳述書提出
その場で、研究室の鍵が付け替えられた
2名の教授は、この日以来、構内に立ち入るときには職員の監視がつき、メールが使えなくなった。3月19日の卒業式にも出席できず、ゼミ生さえ、卒業式当日に初めて事情を知ることとなる。
3月29日 研究室にそれぞれ2名の監視がつくなか、荷物の運びだし終了
改革を求め続け、学部創設時の学部長、学科長解雇となる